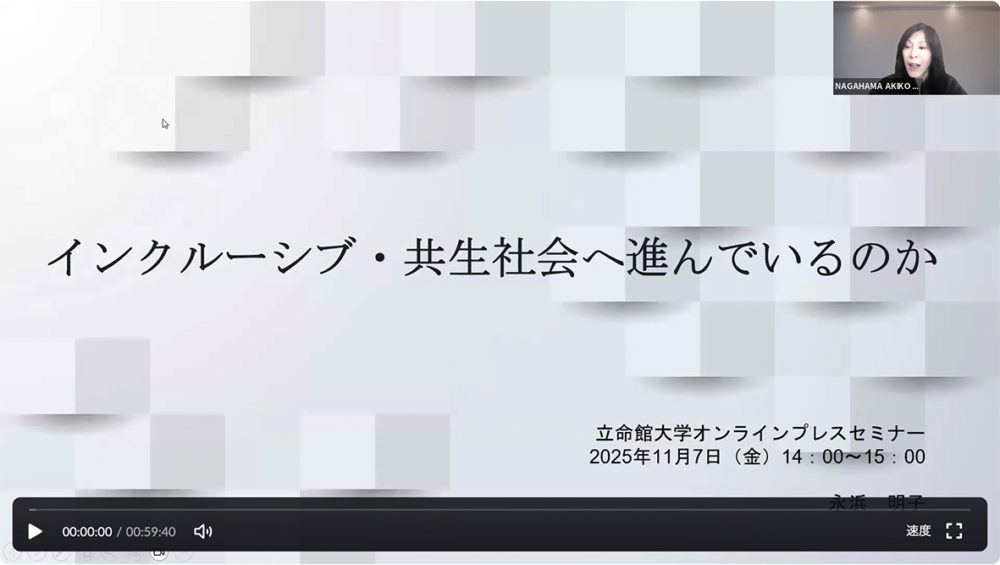つながる
福祉仏教ピックアップ
認知症サポーター養成講座、大学の授業に 佛教大
2024年7月29日
※文化時報2024年6月4日号の掲載記事です。
佛教大学は5月16日、京都市保健福祉局と連携し、学生を対象に認知症サポーター養成講座=用語解説=を開いた。新井康友教授(老人福祉論)の授業の一環で、養成講座を大学の授業に組み込むのは珍しいという。若年性認知症のある芳賀和則さん(62)と下坂厚さん(50)を講師に招き、社会福祉学部の学生12人が認知症と診断された人の心情や不安を軽減する支え方について学んだ。(大橋学修)
認知症サポーター養成講座は、認知症の概要や認知症のある人との接し方などを90分で学ぶ研修で、厚生労働省が推進している。京都市は2006(平成18)年から取り組んでおり、24年3月末時点で15万3千人余りが受講した。
市内の大学では京都光華女子大学や同志社大学が定期開催するなど積極的に協力している。
佛教大学で開かれた講座では冒頭、京都市紫野地域包括支援センター(京都市北区)介護支援専門員の中澤尚子さんが、認知症について解説。認知症の人は、自分自身が記憶していないことに悩み、憤りを見せる場合があると説明し「不安や怒りは『助けてほしい』という救援信号。周囲が対応することで変わってくる」と強調した。
芳賀さんは、若年性認知症と分かってから5カ月ほど落ち込んだことや、通所するデイサービスの利用者に励まされ続けたことを伝え、「気持ちが軽くなり、次の新しい患者さんを励ましてみようと思った。役割ができて、前向きになった」と語った。
認知症の啓発のため、カメラマンとして活動する下坂さんは「自分の役割を見つけ、生きる道ができた。絶望することもあるが、周囲の支えで元気に過ごせる」と話した。

新井教授は「学生は、高齢者施設で実習を行っているが、若年性認知症の当事者には会ったことがない。自分たちの親と同世代の芳賀さんや下坂さんを通じて、若年性認知症のある社会を身近に感じてほしい」と語った。
お寺で学び活発
認知症サポーターは3月末現在、全国で1534万人余りが養成されている。年代別では、授業などで受講する機会の多い10代が436万人と突出して多く、最も少ないのが30代の112万人となっている。
受講者は、認知症カフェの企画・運営に取り組む場合もあるが、認知症があっても住み慣れた地域で不安なく過ごせるよう、さりげなく見守ることが期待されている。
宗教界でも積極的に取り組んでいる例はある。2018(平成30)年には曹洞宗重林寺(静岡県富士宮市)で、僧侶100人余りが認知症サポーター養成講座を受講。同年には山形曹洞宗青年会も開催した。
浄土真宗本願寺派西覚寺(愛知県安城市)の三井求住職は、家族の介護で悩む門徒を見て、地元の社会福祉協議会が主催する養成講座を受講。お寺で門徒向けの養成講座を開くようにもなった。新型コロナで中断したが、再開を模索している。
三井住職は「がんなどの病気と同じで、認知症があることは、恥ずかしいことではない。家族が認知症になっても抱え込まず、専門家などを頼ってほしい」と話した。
京都市内では、認知症サポーターを養成する「キャラバン・メイト」の資格を取得した僧侶はいるものの、大きな広がりにはなっていない。
京都市健康長寿企画課の松井瑞希さんは「地域とのネットワークを持つ宗教者の方の受講に期待したい」と話している。
【用語解説】認知症サポーター養成講座
認知症への理解を深め、地域で当事者を支える社会をつくるため、厚生労働省が2006(平成18)年に設置した制度。当事者やその家族を無理なく支援できる人を、認知症サポーターとして養成する。地域住民、金融機関やスーパーマーケットの従業員、小中高校の児童・生徒らが受講しており、2024年3月31日時点で受講者数は約1534万人に上る。