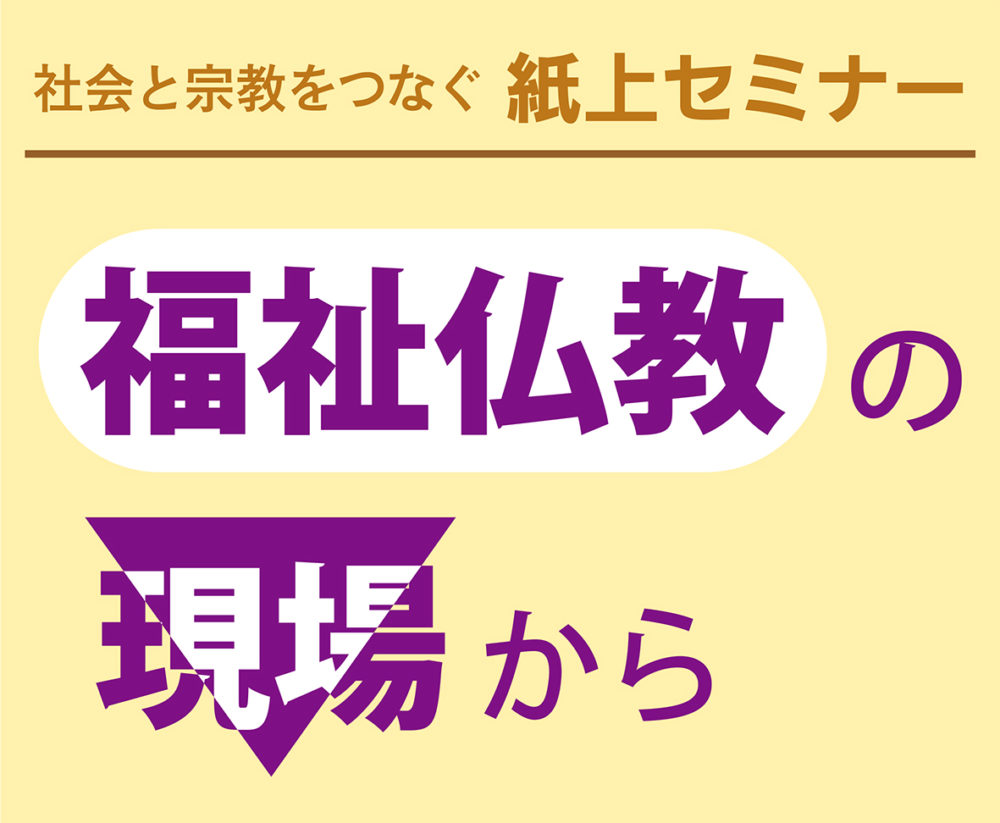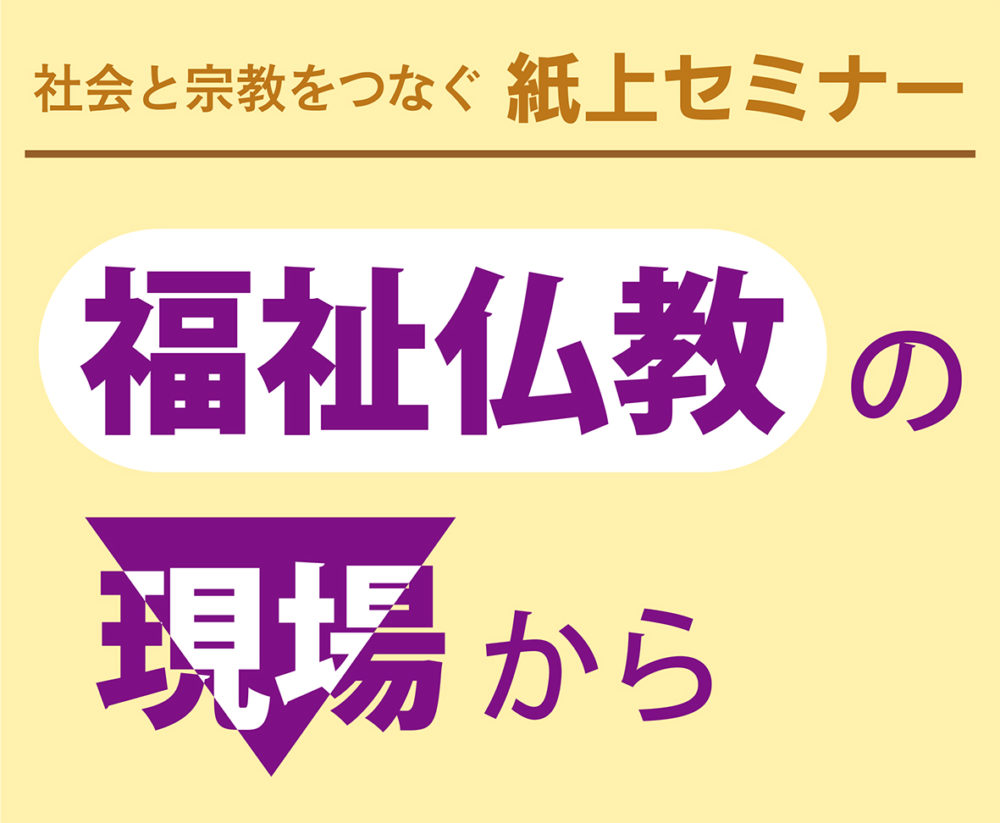読む
「文化時報」コラム
〈91〉苦しみに向き合う布教
2025年2月11日 | 2025年2月12日更新
※文化時報2024年10月29日号の掲載記事です。
生活指導の教員でありながら、息子が手のつけられない非行少年だったという女性に出会った。職場である学校では先生としてふるまい、息子の学校では頭を下げ続ける母親だったそうだ。
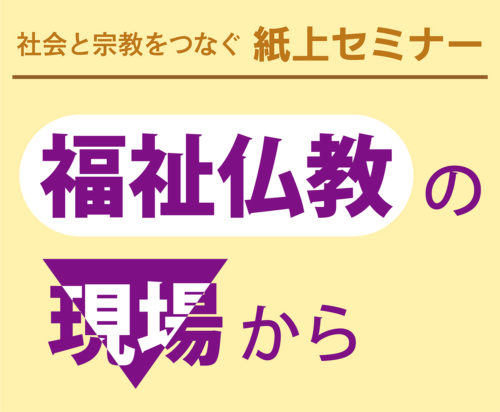
お話を聞かせていただき、女性にとっては大変苦しい時代だったのだろうと痛感した。ただ、子どもにとって学校と家庭は世界の全てである。そのどちらもが安心できない場所であれば、内側にひきこもるか、外側に怒りを爆発させるかだろう。「教育とはこうあらねばならない」と教師に理想を押し付けられると、迷惑なのは生徒である。
第2次世界大戦後に日本語にも翻訳されたアメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトの『菊と刀』は、アメリカの価値観から見た日本の社会は異様であるといい、その異様さは、細かく刻まれた上下関係と恩という名の義務感だと強調している。一度も来日せずに「日本人とは」を書いたもので評価は分かれるが、独特の上下関係と義務感を周辺諸国に押し付けた結果が敗戦であったのかもしれない。
そして、戦後のわが国はアメリカを上位に置いただけで、上下関係と義務感の呪縛からは逃れられていないように思える。
戦後わが国の社会は、学生運動や校内暴力など若者が年長者に反発する道を歩んできた。その若者が今、声を上げることができないほど疲弊し、ひきこもり・不登校として表れている。少子高齢社会では若者の負担が重くなる一方であり、それに加えて上下関係と義務感が若者の生きづらさを助長している気がしてならない。
おそらく釈尊も鎌倉仏教各宗祖も、若者を苦しめる教えを説いたのではないはずだ。
もし、仏教の名のもとで若者を苦しめているのなら、布教は「教育虐待」と言われてもしかたがない。「あなたのため」という呪いの言葉をまき散らしているだけであろう。
社会で何が起こっているのか? 何に苦しんでいる人々がいるのか? そこから目を背けて布教はできないと思う。過去の苦しい時代の話をしてくれた女性は問題が解決したのではなく、苦しみは今も続いていると感じている。