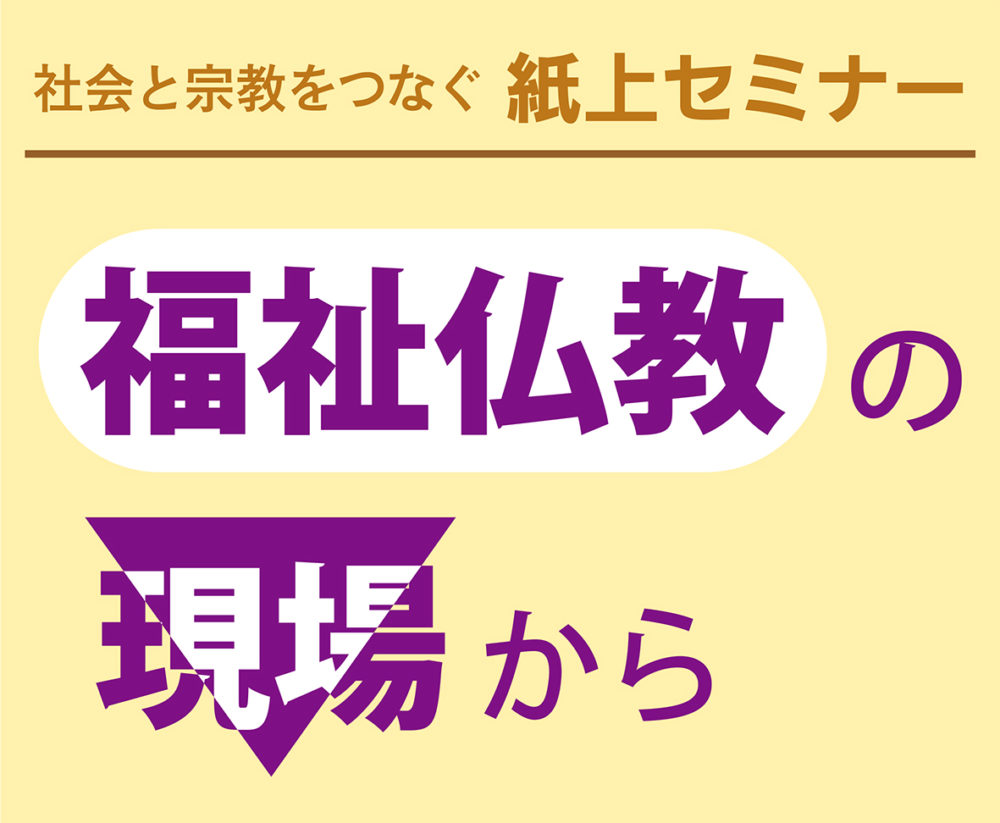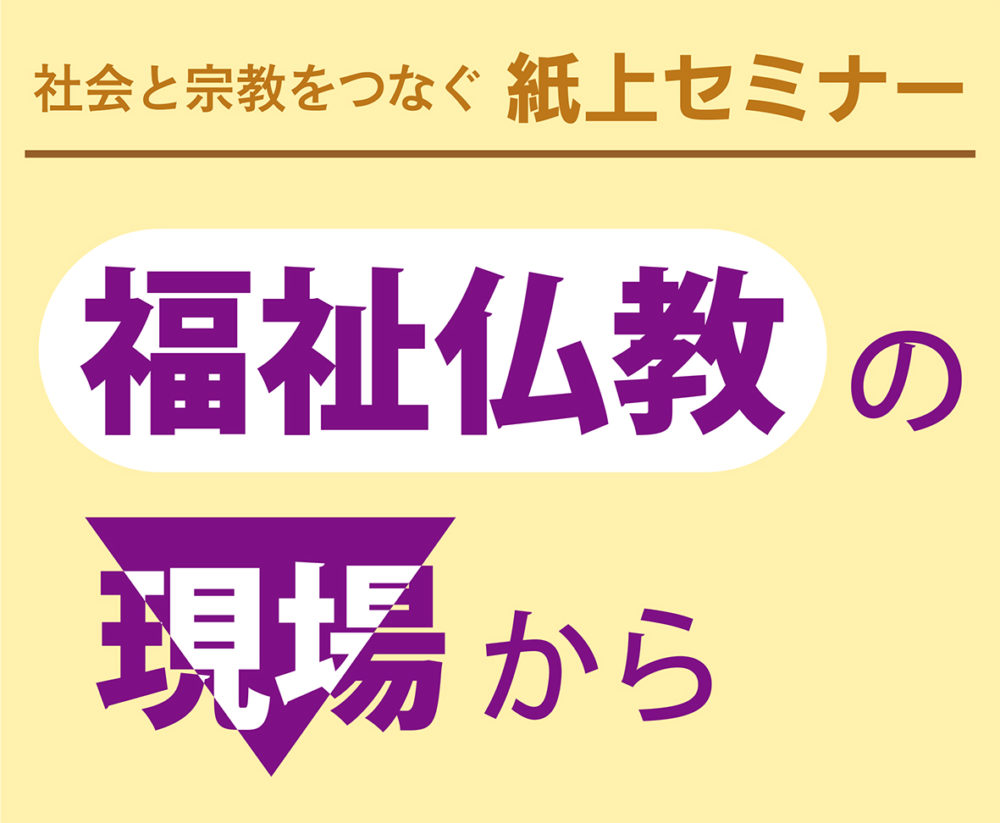読む
「文化時報」コラム
〈98〉介護の勉強を始める
2025年5月17日
※文化時報2025年2月25日号の掲載記事です。
今更ながら、介護職員初任者研修を受講している。僧侶からホームヘルパーに転身するつもりではなく、介護の基本を学んでおこうと思った。
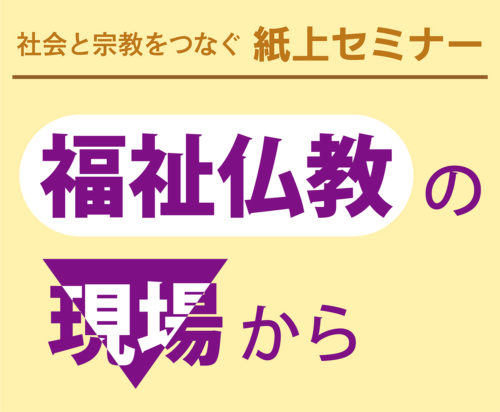
老若男女十数人が一緒に学んでいる。多くの人が資格を得て介護の現場で働くつもりのようだ。介護の現場は人手不足が慢性化している。研修を受ける人は多いが、追いつかないのだろう。超高齢社会である。
移乗やおむつ交換などの技術的なことは別にして、利用者の尊厳を守るなど、考え方はある程度分かっているつもりでいた。
でも、講義が進むにつれ、自分の「慣れ」を痛感している。現場は人手不足なので、ついつい接し方がおろそかになり、それが習慣化して「介護の常識」となってしまっていることがたくさん見えてきた。例えば「寝たきりの人はおむつが当たり前」となっていたり、「食事のときも車いすは当たり前」になって何も感じなくなっていたりする自分を発見した。
福祉仏教の実践を考えている宗教者のみなさんにも、介護職員初任者研修を受講することをお勧めしようと思う。今までできていたことができなくなっていくつらさ、悲しさを少しでも理解していると、法話の幅が広がるような気がする。また、お檀家さんとの接し方も変わるのではないだろうか?
特に男性は介護の勉強をするのに抵抗があるかもしれない。「男なのに」という考えが頭をよぎるからだ。たしかに介護の勉強をする人は女性の方が多いかもしれない。
しかし、60代の男性もそれほど珍しくない。親や配偶者の介護が必要になったために勉強に来る人もいるようだ。宗教者という立場を一度横に置いて、いろいろな境遇の人と水平な立場で出会うのは、福祉仏教を実践するのに貴重な経験になるだろう。その経験は、看護との連携にも生きてくるに違いない。
新しいことに取り組むのは勇気がいる。慣れていることをしている方が楽に決まっている。自分の価値観を改めて見直し、自分とは違った価値観に触れることは貴重だと思う。一歩を踏み出してくれる人が現れることを心から願っている。