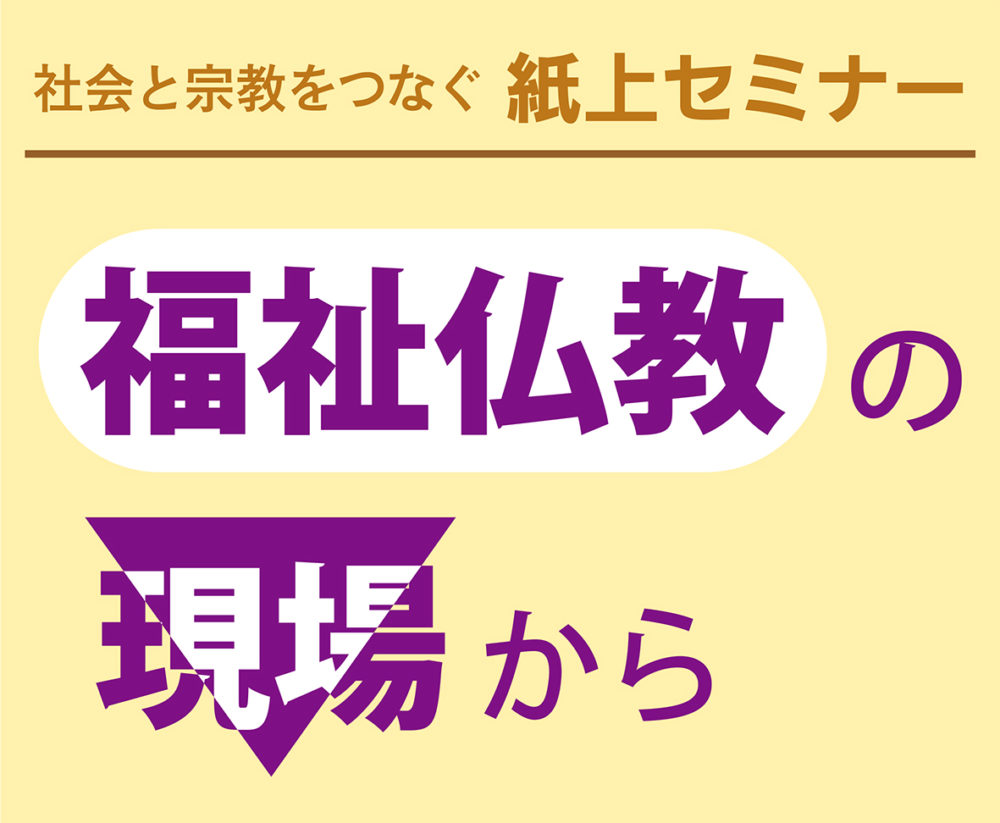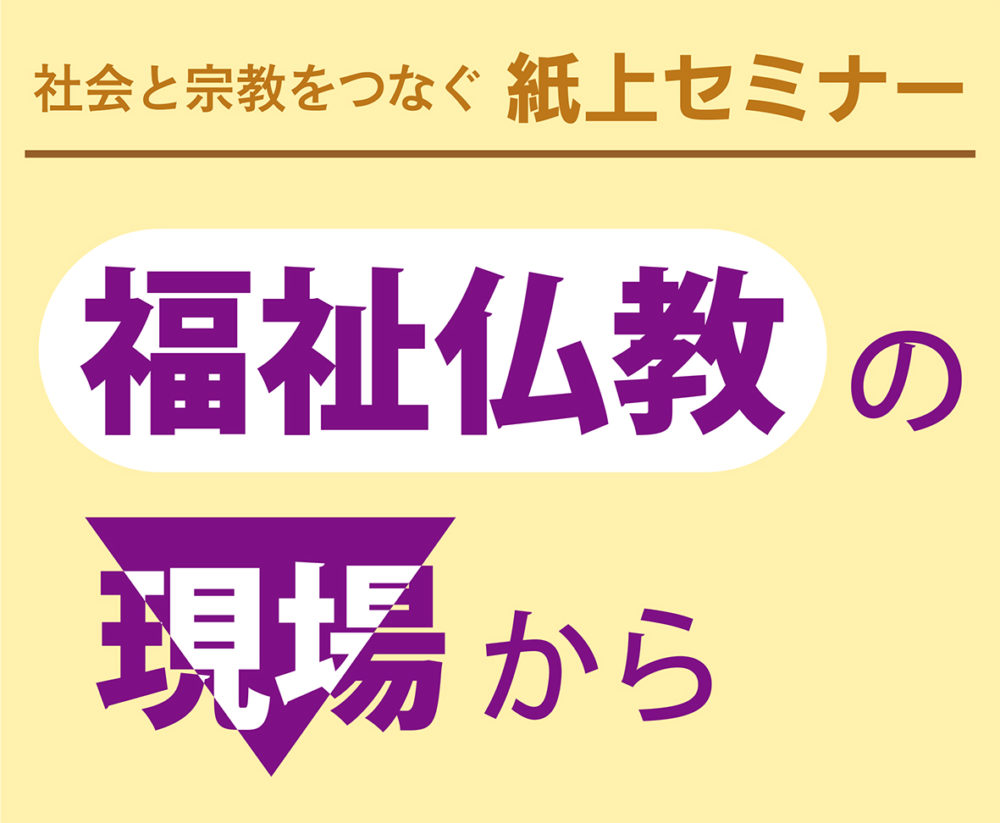読む
「文化時報」コラム
〈100〉垣根を作っているのは
2025年6月25日
※文化時報2025年3月25日号の掲載記事です。
「これは違うあっちは別って垣根作って回ってさ、ご苦労な話だよ!」
3月16日に放送されたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」にて、安達祐実さん演じる大黒屋女将(おかみ)のせりふ。江戸時代に役者は身分が低いとされ差別されていたという。それに憤りを感じた女郎屋の女将が怒りをあらわにした。自分たちも汚らわしいと差別されている身である。
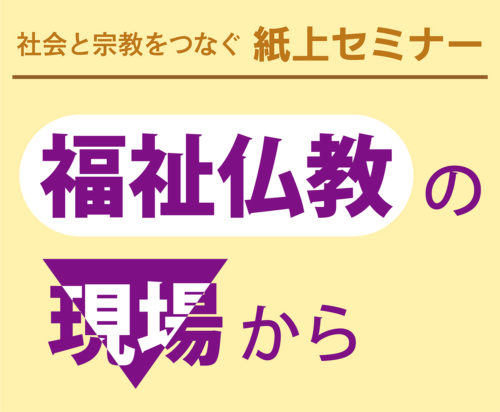
差別ではないが区別することが正しいと思ってしまうのが医療や福祉の世界かもしれない。支援する人(専門職)とされる人(利用者)とは明確に区分される。それに異を唱えるグループの集いがあった。「第25回地域共生ケア全国ネットワーク研究交流フォーラムin大阪」である。
3月14日と15日の2日間にわたり大阪・上本町たかつガーデンをメイン会場として、全国各地からオンラインを含めて両日で延べ300人を超える参加があった。筆者は実行委員の一人として運営に携わった。
また、登壇者として発言する機会もあったので「社会資源としてのお寺の活用」について伝えた。その後の交流会では、いろいろな人からお声をかけていただいた。多くの人が「医療・福祉にお寺が関わっていることに驚いた」という感じであった。むしろ驚いたのはこちらの方であるが。
多くの方が関心を示してくださったのは「惣墓(そうぼ)(寺院内の共同墓)」であった。無縁社会といわれるようになってから久しいわが国で、身寄りがない人の納骨をたくさん引き受けていることに共感してもらえた。それほど医療や福祉の現場では切実な問題となっている。
「どこのお寺でも引き受けてくれるのですか?」と毎度おなじみの質問が飛んできた。「引き受けてくれるお寺はまだまだ少ないと思いますが、お近くのお寺にぜひご相談なさってください」と返事しておいた。遺骨と冥加(みょうが)金をお持ちになれば、多くのお寺は引き受けてくれるだろう。
ただ、医療や福祉関係者が望んでいるのはもっと別のことのような気がする。お寺側が作っている垣根をまずは外してほしいのではないだろうか。