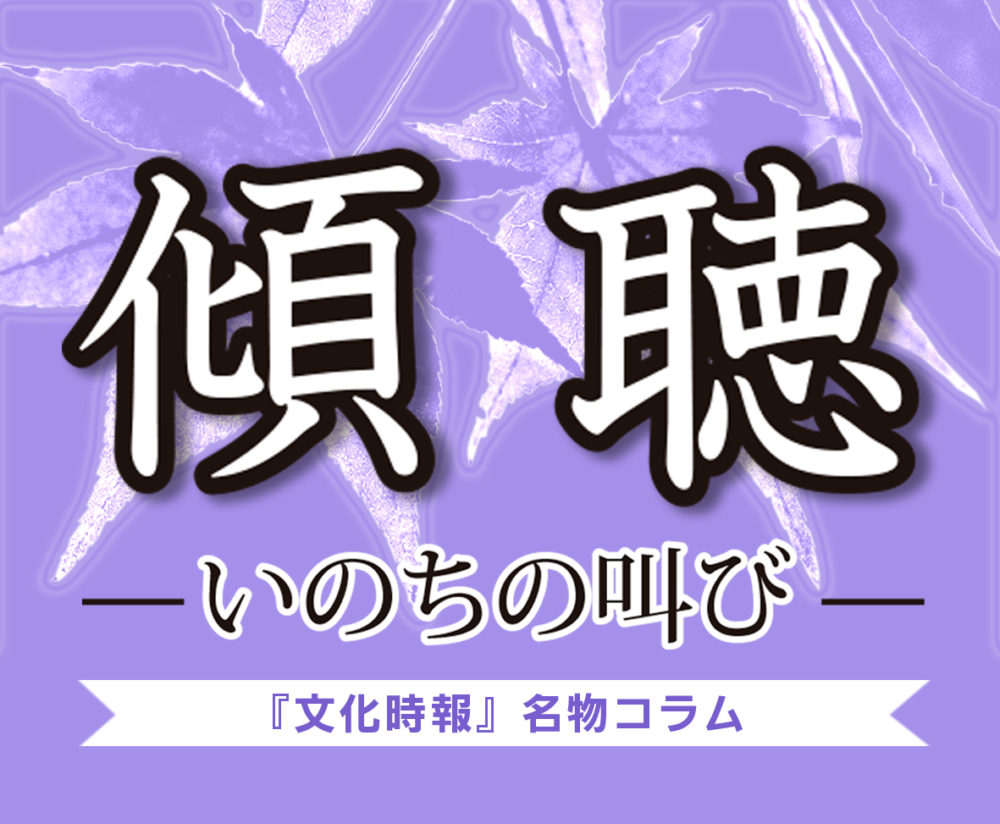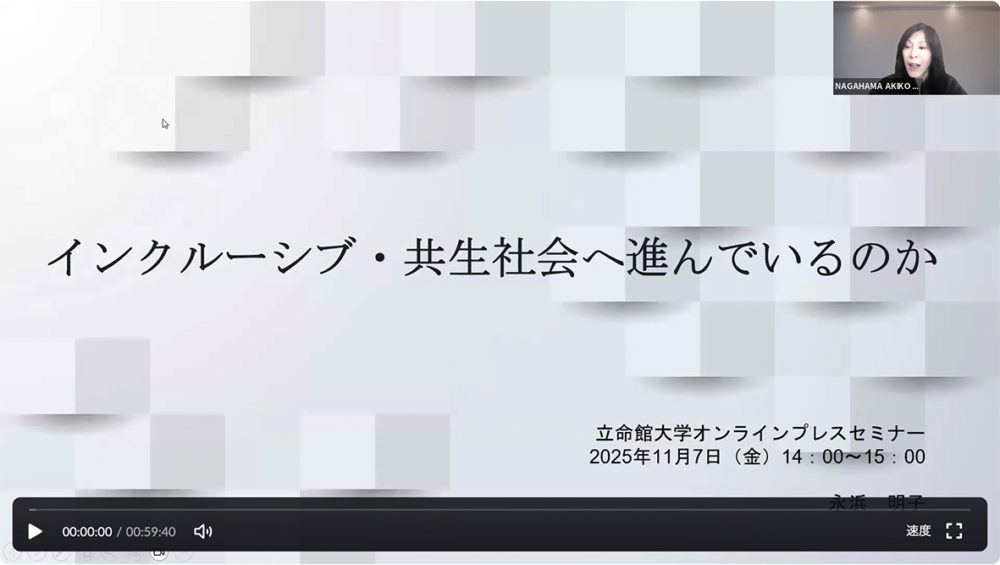読む
「文化時報」コラム
〈2〉やり遂げた経営者
2022年9月2日 | 2024年8月5日更新
※文化時報2021年9月2日号の掲載記事です。
先日、一つの孤高な魂が旅立ちました。
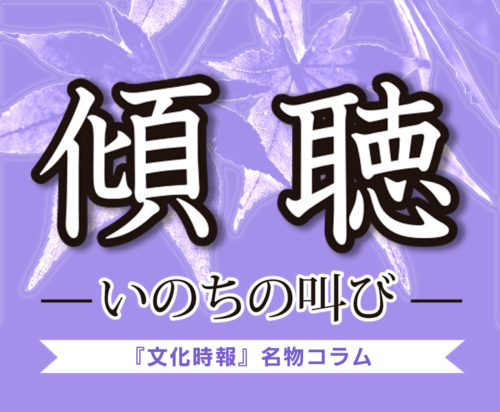
60代後半のAさんは末期の肺がんで、余命3カ月の宣告を受け緩和ケア病棟に入院してこられました。会社の経営者としてまだまだ現役だったこともあり、病棟のスタッフや仕組みに対して、厳しい提言を躊躇(ちゅうちょ)することなくぶつけてこられることもしばしば。でも、どれもこれも的を射た正論でした。
そして、折あるごとに、私を相手に「死とは何か」「生きるとは何か」を語ってくださいました。実に博識で、仏陀(ブッダ)は何と言ったか、キリストは何と言ったか、ニーチェは……と深い話が続きます。時に、あまりに物を知らない私に「ちょっと、君、そんなことじゃダメだろう」と叱責が飛んでくることもありました。
そんなAさんが、ある夜、ぽつりとこうおっしゃったのです。「偉そうなことを言っているけど、私も最期は乱れると思う。それだけが、心配だ。最期までしっかりやり遂げられるよう、その時は君、頼んだからね」。穏やかに広がる笑みを拝見しながら、とはいえ何をしたらいいのか分からないまま、ただただ、うなずきました。
別の夜にお訪ねすると、ギャッジアップし頭側を高くしたベッドに寄り掛かるように座っておられます。肺がんの末期の苦しさは、大変なものです。それでも、私をご覧になると「やあ」とうっすら笑顔。思わず「しんどそうですね」とお声掛けすると、「これも修行だよ」としっかりお答えになりました。その後は、二人とも黙り続け時折目を合わせるだけの時間が、静かに過ぎるだけでした。
翌日、Aさんが旅立たれたと連絡。あの静かな時間から、わずか5時間後のことです。乱れるなんて、とんでもない。最期の最期まで、一糸乱れず「死」に向き合い切られた。こんな崇高で孤高な魂を拝見したことがありません。
人は、こんな高みまでいくことができるのだ。身をもって示してくださったAさんに、手を合わせ、ひたすら拝礼させていただくばかりです。