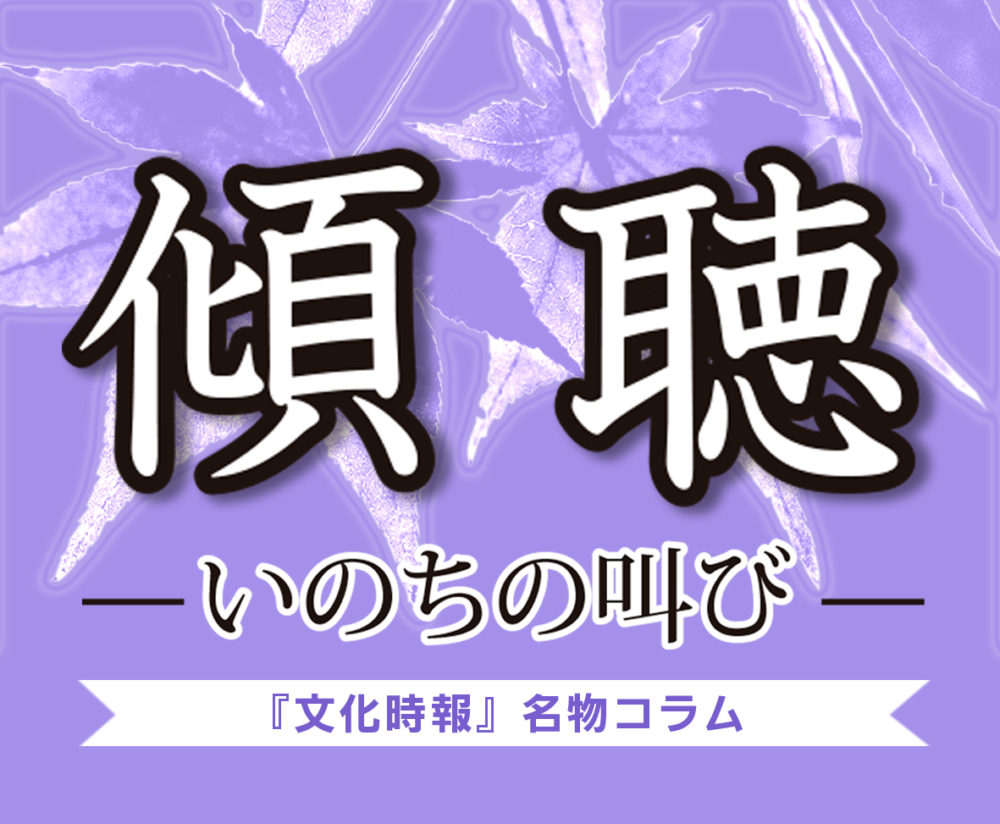読む
「文化時報」コラム
〈7〉私も声が聞きたい
2022年10月7日 | 2024年8月5日更新
※文化時報2021年11月11日号の掲載記事です。
昨夜の出来事ですので、プライバシーをお守りするために、一部フィクションを交えて書かせていただきます。
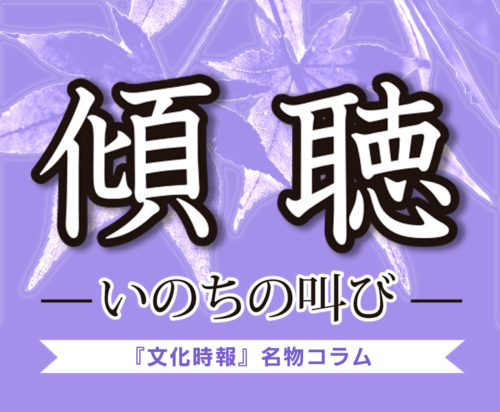
80代半ばのその方は、末期の肺がんです。ベッドに横になり、酸素を吸入していらっしゃるにもかかわらず、あえぐように話し始めました。
「毎晩寝るときに拝んでいるんだ。このまま、もう目が覚めないようにって。天国なり地獄なりどっちでもいいから早く連れてってくれって」。思わず目をそらしたくなるほど、真っすぐに私の目を見ておっしゃいます。「もう、目が覚めてもしょうがないんだよ。生きていたって、いいことなんてあるわけないんだ。だって、治らないんだから」
おっしゃるとおり、現代医学はもはやこの病を治すことはできません。
「どうしたらいいですか。苦しめってことですか(ぜぇぜぇ)。死ぬまで苦しむしかないんですか(ぜぇ、ぜぇ、ぜぇ)」。伝わってくるのは、怒りではありません。底なしの、涙なき慟哭(どうこく)です。「悪いことは、何ひとつしてこなかった。一生懸命働いてきたつもりだよ。なのに、なんでこんなことになるんだろう(ひゅっ、ひゅっ、ぜぇ~)。自分で死ぬ勇気もなければ、こんな手じゃなにもできない(ひゅ、ひゅ)」。お顔の前に持ち上げた手が震えています。
「あなたはお寺さんでしょう。あなたの信じている仏様は、こういうとき、何て言うの?(ぜぇ、ぜぇ)教えてよ。教えてくださいよ(ひゅう~、ひゅう~)」。私は喉が詰まり、一言も話せませんでした。
医師の判断とご本人の同意をもって、まもなく薬を使って意識レベルを落とすことになるでしょう。現代医学が持っている緩和ケアという医術です。でもそれで、この方のこの苦悩は、本当に楽になるのでしょうか。
私たちは、薬でこの方を黙らせて、この叫びを聞かずに逃げるだけでは? そうではないことを、祈るばかりです。私も、仏様の声が、聞きたいです。