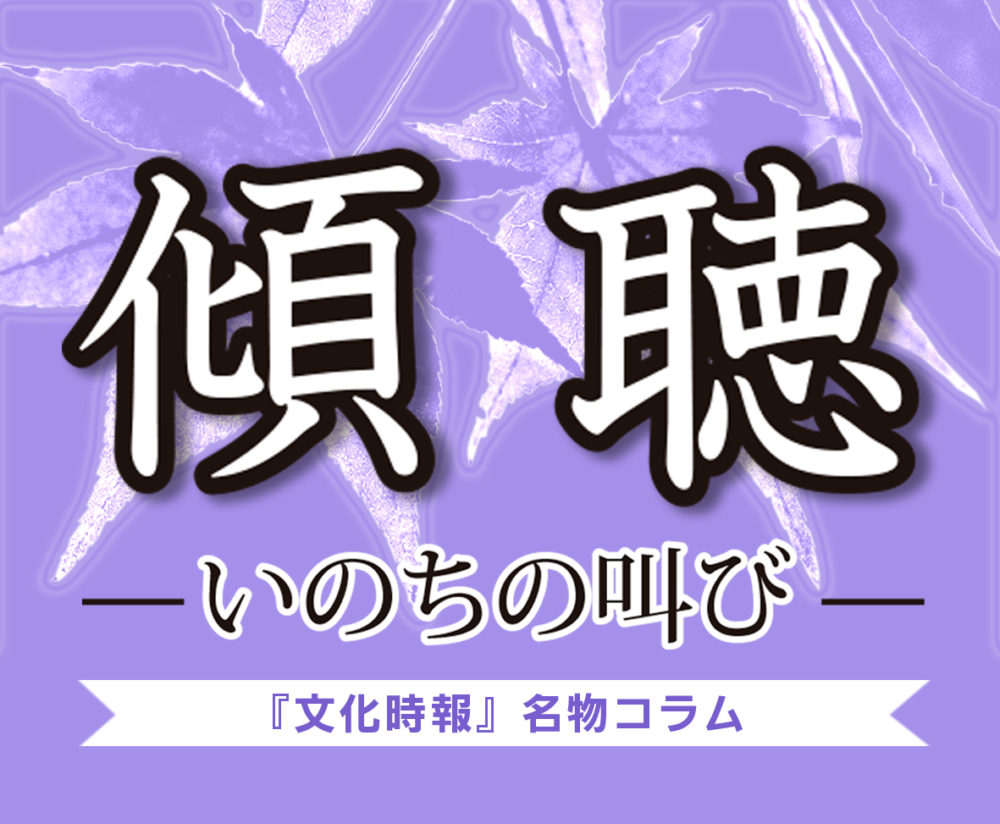読む
「文化時報」コラム
〈8〉心がよどんでいないか
2022年10月14日 | 2024年8月5日更新
※文化時報2021年11月25日号の掲載記事です。
先日、20年にわたりイギリスで暮らしていた知人が帰国し、隔離期間を無事終了したというので、久方ぶりに会いました。積もりに積もった話をしていると、ふと彼女が「そういえば、日本に帰ってきてびっくりしたことがある」と言い出しました。いったい何にびっくりしたのかと問うと、「電車が人身事故で止まりすぎる」と。たしかに、私が常々利用している路線も、人身事故で遅延することが珍しくありません。特に年末に向けては、遅延ありきで時間設定をする用心も必要なほどです。
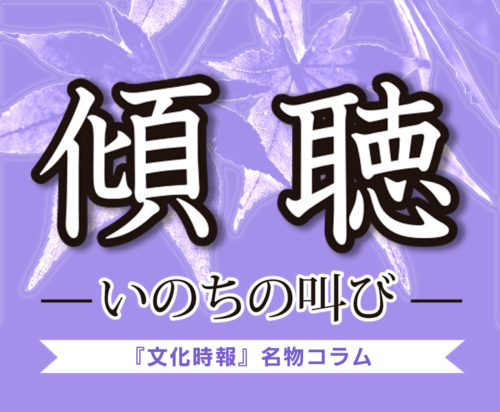
「でも、もっとびっくりしたのは…」と彼女が続けます。「人身事故で止まるという車内アナウンスを聞いた日本人が、舌打ちをして、すぐ携帯をいじり始めること」だと。
バケツの水を頭から浴びせられたような気分でした。「遅延ありきで時間設定をする用心」などと考えた私の思考は、そこ止まり。遅延の裏にある「逝った命」を、想像すらしていなかったからです。
一体いつから私の心は、こんなに干からびていたのでしょうか。次々となだれ込んでくる情報を、己の損得のみを基準として右から左へと受け流す。心の表面にさざ波が立ちはするものの、それさえも直ちに何事もなかったように消えていきます。二つ三つ先の駅で今、一つの命が終わったというのに、私の心は愚鈍によどんだままです。
感傷的な自己満足で、良い人ぶろうとしているわけではありません。「救えた命があった」などと言うつもりも、さらさらありません。きっと何をしても、逝くと決めてしまった命を留めることなど、できはしなかったでしょう。
でも、その命が生きてきた時間の質量に思いをはせ、来世を願って手を合わせる。そこを忘れてしまったら、いけない気がしたのです。忘れてしまっていた自分が、心底怖くなったのです。
しっかり、歩いていこうと思います。