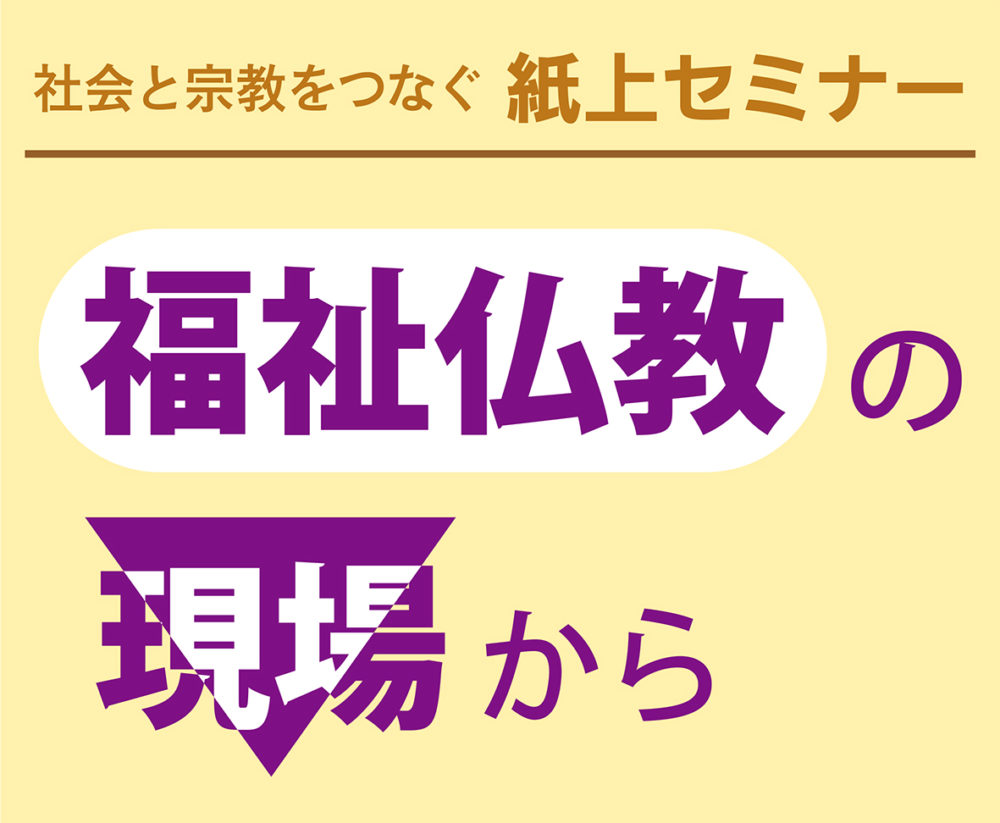インタビュー
橋渡しインタビュー
片麻痺で筆文字の楽しさ伝える 大賀佳奈さん
2023年7月10日
札幌市の大賀佳奈さん(47)は幼少期に脳腫瘍を発症し、2回の手術を受けて左麻痺になった。幼稚園から大学まで、健常者と同じ生活を送っていたが、思春期にはいじめや差別を受けて自分自身を否定したくなることもあった。現在は結婚して2人の息子を育てながら、「伝筆(つてふで)」と呼ばれる文字アートの認定講師として、多くの受講生にその魅力を伝えている。
くせ字を魅力ある字に
「誰しも魅力がある」「自分の殻を破る」
丸みを帯びたユニークな筆文字で、温かな思いを伝える。コツさえ覚えれば、誰でも自分のくせ字を魅力ある字に変えられる。黒だけでなく、赤や青など色のバリエーションも豊富で、アート性の高い表現が可能だ。

そんな「伝筆」に大賀さんが出会ったのは、保険代理店でもらった1枚のはがきだった。優しいメッセージに心が癒やされた。
「私にもできるかもしれない」。元々書道をやっていたが、書道よりも個性が表現されるアートに魅力を感じた。自分で調べて伝筆講座を受講。書いた作品を友人に送り、会員制交流サイト「フェイスブック」などで発信すると、友人から「どう書けばいいか教えて」と頼まれたことが、講師になるきっかけとなった。
思えば、幼い頃から自分の思いを伝えることに恐さを感じていた。それが伝筆では、自分の素直な気持ちが形になり、人を喜ばせられる。
今では色紙に書いてほしいと依頼される。カレンダーを制作したり、自分で講座を開いたり。主婦を中心に多くの人が大賀さんから学んで、笑顔で作品を持って帰る。「人の役に立っている」と実感できる瞬間だ。
「筆文字はそれぞれの個性が光ります。描くことで自分の良さが作品に写し出され、一人一人の可能性が広がると信じています」
最初からあきらめないでチャレンジ
大賀さんが脳腫瘍を発症したのは3歳の時。足を引きずり、突然吐くなど体調に異変が見られた。北海道大学で手術を受けて腫瘍を取り除いたものの、左半身に麻痺が残った。
懸命にリハビリし、足に装具を付けて、幼稚園へ通い出した。健常の子どもたちと一緒に過ごし、好奇心旺盛な性格からどんなことにもチャレンジした。

「いつもみんなと同じことをやりたかったんですよね。小学生の頃もマラソン、スケート、ドッジボールと全て仲間に入って、必死に付いていきました。まずはやってみて、自分なりのベストを尽くしました」。音楽の授業で使うリコーダーも、母親が片手で吹ける笛を探してくれたおかげで、一人で演奏することができた。
両親は娘の成長する姿に、笑顔を見せた。親の喜ぶ顔を見たい、家族の期待に応えたいと、子どもながら何事にも全力で臨んだ。
私の居場所がなかった
そんな大賀さんに、試練が待ち受けていた。中学生になると、同級生にからかわれ、いじめに遭ってしまったのだ。小学生の時には一緒に遊んでいた友人たちも、離れていった。
家に帰って家族に相談すれば、怒った父親が学校に乗り込んで行くのは想像ができた。ますます状況が悪化することを恐れ、ただ耐えるしかなく、どこにも居場所がなかった。
「私自身が生きる場所を見失い、思ったことを口に出せず、殻に閉じこもってしまいました」
障害のため、幼い頃から母親に手を借りることが多かったが、成長するにつれ、自分の存在が周りに迷惑をかけていると思い込むようになった。明日が来るかも分からないほどつらい時期を数年送った。中学生でもおねしょをするほどの精神状態に陥ってしまった。
いじめを乗り越えられたのは、かつて通っていた幼稚園に隣接された教会学校の教えだった。「小学生になってからも、友達と時々、教会学校に通っていました。私はキリスト教の洗礼を受けていませんが、その時の教えが私を支えてくれたんです」
人は生かされている。自分が生きることには、意味がある。
大賀さんは「いつか幸せになる」と心に誓い、いじめを乗り越えた。

自分のことを誰も知らない土地へ行きたいと、大学は茨城県に進学した。初めての1人暮らしを経験し、福祉やカウンセリングについて学んだ。後に結婚する夫ともこの時に出会い、楽しいキャンパスライフを手に入れた。
絶対にこの子を産む
大学卒業後、北海道に戻り乳製品の会社に就職。障害者雇用が初めての部署で、先輩や上司との関係にストレスを抱えながらも「仕事だけは負けない」と、5年働いた。
その後、結婚して妊娠したが、両親からは「産むのか、おろすのか」と厳しい言葉を突き付けられた。片麻痺の女性が子どもを育てることがどれだけ大変なことか―。両親なりに娘の将来を心配しての発言だったが、大賀さんにはショックな言葉だった。
「絶対この子を産む」。その気持ちは、断固として揺るがなかった。
出産後は右手しか使えない子育てを必死にこなした。おむつ替えも片手で行うため、赤ん坊のお尻に顔を近づけた。「うんちが顔に付くこともよくあって」と今では懐かしい笑い話だ。
散歩をするにも、子どもが飛び出したらすぐに追い掛けられないので、背中にひもを着けて移動していた。かわいそうと見られることがあっても、全てはわが子を守るためだった。
現在、2人の息子は大学生と中学生になった。「地域の方々にも助けてもらえたから、子育てを続けられた」と大賀さんは言う。
実は大賀さんは、片麻痺以外にも左目の視野が狭くて動体視力が弱い。聴力も良くないという。現在も体調と相談しながら、今できることを楽しんで生きていきたいと願っている。
「昔は周りの目を気にしていましたが、大人になって同じ当事者やさまざまな障害を持った方々に出会いました。見方を変えれば皆さん素敵な能力を持っています」
「伝筆」の他にも一昨年、友人に誘われて出た「ミセスジャパン2021北海道選考会」で特別賞を受賞。ウオーキングやスピーチの練習に励み、自分を変えたいと意を決してドレスを着るなど、アクティブに過ごしている。

「みんな違ってみんないい。金子みすゞさんの詩のように、障害があってもなくても十人十色。自分の個性であると思って大切にしてほしい。自分のやりたいことには諦めないで、チャレンジしてください」
「障害者だからかわいそう」と思われがちだが、誰もが障害や病気を抱える可能性はある。たとえそうなっても、安心して自分らしく生きられる社会であってほしいと考えている。
「私の障害は、今世でいろいろ学ばせてもらうための、神様からのサプライズだったと思うことが増えました」
かつて障害やいじめに悩んだ大賀さんは今、とても輝いている。たくさん傷ついたからこそ、その筆文字が人々の気持ちを温かくさせるのだろう。