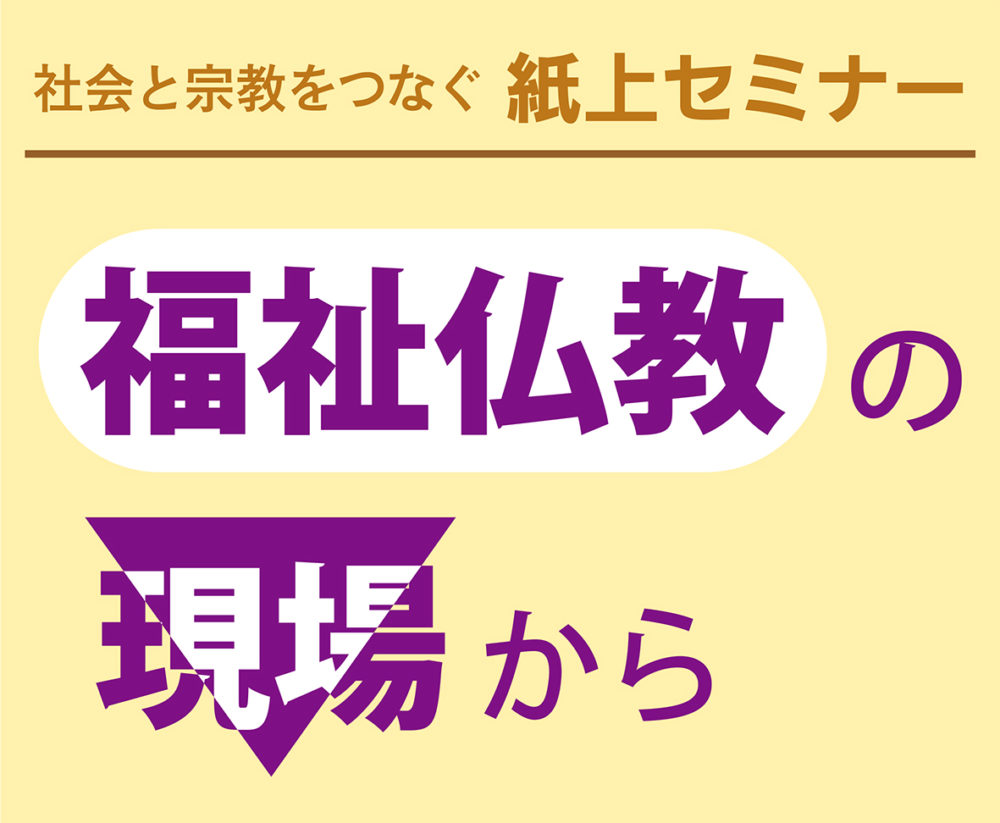インタビュー
橋渡しインタビュー
子どもと弁護士でつくる演劇「もがれた翼」
2023年12月27日
日本が子どもの権利条約を批准したのは1994(平成6)年。以来、子どもは大人と同じように、一人の人間として守られ、医療・教育・生活などへの支援が保障されるようになった。大人は子どもの意見に耳を傾け、思いを尊重しなければならないが、必ずしも誰もができているわけではない。そうした中、東京弁護士会は子どもたちと弁護士でつくる劇「もがれた翼」を上演してきた。28作目の今回のテーマは「子どもの声を聴く」。出演した松原拓郎弁護士に話を聞いた上で、舞台を鑑賞した。(飯塚まりな)
主人公はネグレクトを受けた女子高生
10月7、8日、東京都豊島区東池袋の「あうるすぽっと」。「もがれた翼part28『シン・フォニィ』」は客席が満員になり、ロビーにあふれるほどの人だかりができた。
役者は学生3人を除いて全員が東京弁護士会に所属する弁護士。日ごろから子どもたちを取り巻く犯罪や非行、家庭や学校の問題に向き合っている。

主人公のあいりは高校3年生。父親を早くに事故で亡くし、精神的に情緒不安定な母親との2人暮らしだ。
自称ユーチューバーと語る母親は、自己啓発を促す動画を自撮りしている。明るい姿を見せる日もあれば、酒に溺れてあいりに暴言を吐き、家事ができずまともな食事も作れない日もあるほど精神が崩壊していた。
ネグレクト(育児放棄)になった母親からアルバイト代もほぼ取られてしまうあいりは、家や学校に居場所がなく、今の生活に限界を感じていた。
その頃、アルバイト先で知り合った同級生の女の子、田中と仲良くなる。偶然、高校も一緒で話も合い、唯一心を許せる友達ができたことで楽しい時間を過ごすようになる。
「うちの親、頭おかしいんだよね」。ある日、元気のないあいりが口にした言葉。初めて聞く壮絶な家庭環境に驚く田中だが、高校生なりに必死に調べて「子どもシェルター」(緊急避難場所)を探し出す。
田中のおかげで、いったんは家を出てシェルターに身を隠し、母親から逃れたあいり。だが、母親を慕う気持ちや先行きの不安と葛藤していた。

緊急避難場所から自立支援へ
日本には2023年12月時点で、子どもシェルターが22カ所ある。最初の子どもシェルターは04年、東京に設置されたという。スタッフが常駐し、入居した子どもたちの様子を見守りながら、衣食住の世話や金銭面を支える。
個室が用意され、家庭的な暮らしが与えられるが、滞在期間は約2カ月が目安。場所は特定の関係者にしか知らされず、一見ごく普通の民家で「今日帰る所がない」という子どもたちが数人入居している。
子どもシェルターを出た後は「自立援助ホーム」に移るなど、就労しながら自立を目指していく子どもをサポートする仕組みがある。
就職活動をして、働きながら貯金し、ゆくゆくはアパートで暮らして自立を目指す。家事やコミュニケーションなど生活で必要なスキルはスタッフがそばで教える。ここでも滞在期間は半年〜1年程度が目安とされている。
一般的には、親元で学業や遊びを謳歌(おうか)する子どもたちが多くいる。そんな中、親に頼れない彼らは、人並み以上の努力をして信頼できる大人を探し、自分の生活基盤を整えなくてはならない。
また、親から身を守るためシェルターにいる間は、一時的に子どもたちはスマートフォンを使えなくなる。肌身離さず持っていることに慣れたスマホを手放せないという理由で、シェルターへの入居を拒む子どももいるという。

一人の子どものために、全力で
もう一人の主人公、あいりの担当弁護士の大谷は、雑談が苦手で不器用な30代。教育熱心な家庭で育ち、弁護士になったが自分の思いをどこか伏せてしまい、妻やあいりの気持ちを読み解くことに難しさを感じている。
シェルターに身を寄せたあいりを中心に、担当弁護士やシェルターのスタッフ、児童相談所の職員との会議が行われる。
「あいりさんの気持ちが大事だからね」と口に出す一方で、大人の事情とあいりの心の声が交差する場面が印象的だ。
劇中では、あいりの母親が持ち家を手放すことや、いずれは生活保護を受給すると決めたこと、あいりが自立援助ホームの見学の帰りに「できれば他のホームも見学できますか?」と遠慮がちに児童相談所の職員に尋ねる場面などが、現実にもありそうな感じで伝わってきた。
「自分を苦しめる母親から離れたい、でもこの先一人でやっていけるのか」と思い悩むあいりと、沈黙から見えるあいりの本音をつかもうと健気(けなげ)に寄り添う大谷。2人の成長も見られる。

話を聞かせていただいた松原弁護士は今回、役者の一人として参加。今回が3回目の出演だという。自身も虐待事件などで多くの子どもたちの弁護を担当している。
昨年6月に「こども基本法」が公布され、今年4月に施行されたことを踏まえて、松原弁護士は次のように語る。
「子どもはかわいいだけでは守れません。子どもの心は特に複雑で、思っていることと違うことを話したり、黙ってしまう子もいます。言葉にすることだけが全てではなく、沈黙の背景に何があるのかを考えることが大事です。人の話を聴くのは実は難しいことですが、劇を通して子どもについて考えるきっかけになってもらえたらと思います」
観客は福祉職や新人弁護士も多く、担当するケースの参考にもなっているという。
舞台の上では、それぞれの立場から見える状況や心境が、分かりやすく観客に伝わってきた。役者全員が一人の子どものために動き、幸せに生きてほしいと願っていることがひしひしと感じられた。
「万引から殺人までさまざまなケースがありますが、どれも悩んでいる子どもが起こしたことに変わりはありません。発達障害や知的障害の問題もあり、苦しみを消化できない子どもたちを見捨てるわけにはいかないのです」
一見、どこにでもいる普通の子どもたち。でも、家の中に入ればどんな家庭環境で育っているかは知る由もないのが現状だ。未来を担う彼らの明日にもっと興味や関心を持ってもらえたら―と、松原弁護士は話していた。