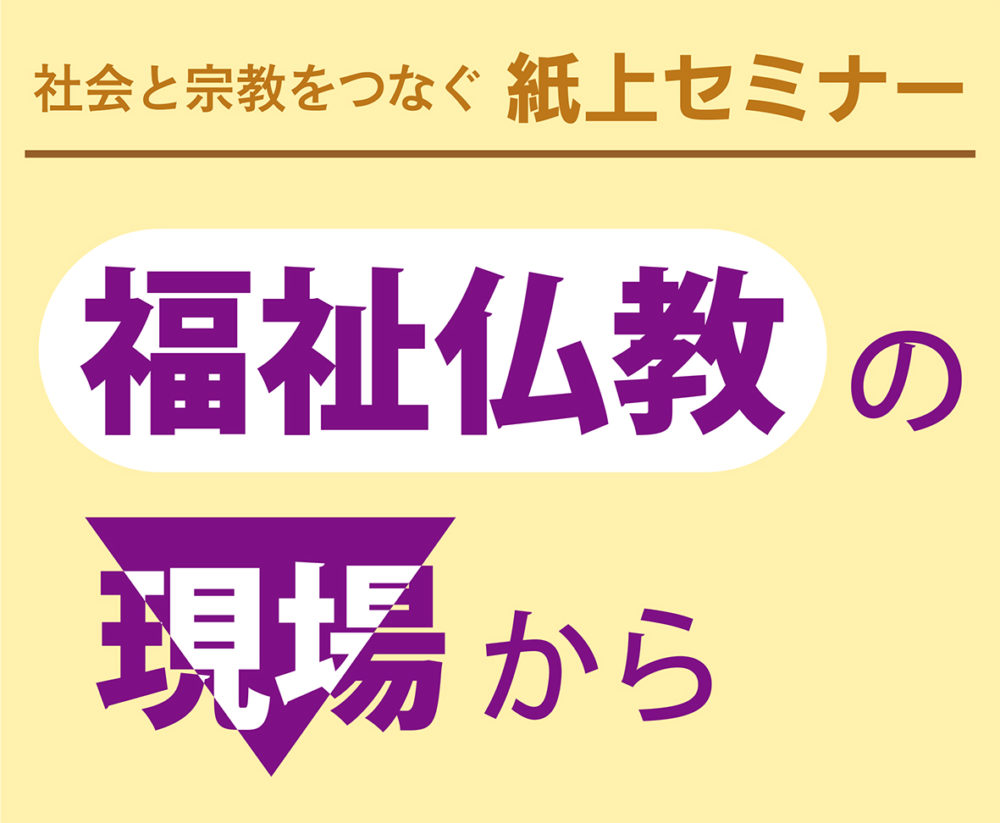つながる
福祉仏教ピックアップ
お寺で防災ワークショップ 要援護者への対応学ぶ
2025年6月30日
※文化時報2025年3月18日号の掲載記事です。
大阪市住吉区の浄土宗願生寺(大河内大博住職)は8日、お寺を災害時の一時避難場所として生かす防災プロジェクトの第3回ワークショップを開催した。地元の町会役員や行政職員、小学生と保護者、視覚障害のある人や学識経験者ら多様な立場の約30人が参加。高齢者や障害者といった災害時要援護者への対応について学び、グループディスカッションを行った。(大橋学修)
願生寺は医療的ケア児=用語解説=の一時避難場所となれるよう、2021年9月に防災プロジェクトをスタート。当事者と家族、地域住民らが参加する懇話会やワークショップを重ねてきた。

この日は、住吉区役所地域課の東森慶子氏が地域支援員による災害時要援護者の見守り活動について、住吉区保健福祉センターの柳澤杏衣(あい)氏が災害時個別支援計画について、それぞれ説明。大河内住職は、医療的ケア児を育てる潮見純さんの手記を代読し、手助けが必要なことが地域に知られていない不安を訴えた。
発表を聞いた地元町会の役員らは「災害時要援護者のリストがあることで情報共有できる」「リストを生かした訓練を行うことが大切だ」と話した。
一方、グループディスカッションでは、地域支援員の住民が「役割を伝えられていないため活動しておらず、個人情報を受け取ることに責任の重さを感じる」、視覚障害のある人が「マンションに住んでおり、地域とのつながりがない」と課題を伝えた。
かまどベンチで交流
ワークショップの後には、炊き出しができる「かまどベンチ」の基礎作りを、参加した小学生が中心になって行った。

かまどベンチは、レンガを積み上げて木製の座面を設けることで、平時はベンチとして、災害時はかまどとして使う。参加者からは、完成後は炊き出しのイベントを開催してマンションの住人らと交流する機会をつくろうというアイデアが出された。
防災プロジェクトに参加している防災・災害時支援コンサルタントの園崎秀治氏は「さまざまな世代が参加し、アウェー感を覚えることのない関わり合いができている」と評価。宗教者の災害支援に詳しい稲場圭信大阪大学大学院教授は「苦労もあったが、何年もかけて今に至った。人と共に生きようとする強さが大切だ」と話した。
【用語解説】医療的ケア児
人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、痰(たん)の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童。厚生労働省によると、2021年度時点で全国に約2万180人いると推計されている。社会全体で生活を支えることを目的に、国や自治体に支援の責務があると明記した医療的ケア児支援法が21年6月に成立、9月に施行された。